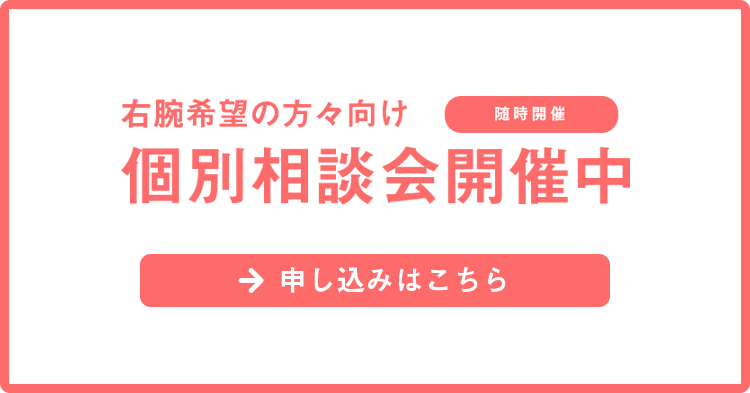リーダーがビジョンを語る
酒をしぼった瞬間に生まれた「使命感」
気仙沼でお酒をつくりつづけて100年。男山本店では、今日も酒造りが続いている。津波は本社を飲み込み、蔵の数メートル手前まで迫ったが、貯蔵タンクなどに被害はありませんでした。年の暮れに、蔵の上にある事務所でお話をお伺いしました。【株式会社男山本店・菅原昭彦】

―今はどのような時期なのですか。
2011年産の新しい米を仕込む時期です。普段は11月から始めて、2〜3月末まで酒をつくり続けますが、今は新年を迎える前の最盛期といったところですかね。正月になると休みを取って、正月明けからは一番良いクラスの酒造りに取りかかります。「寒造り」といって、日本酒造りに一番向いているのが1〜2月、特に空気が一番冷たくてきれいな1月ですね。今回は震災の影響もあって、9月1日から酒造りを始めました。少量ではありますが、限られた設備の中で例年より2か月前倒しで仕込みを始めました。
―地震のときは何をされていましたか?
本社の中にいました。事務所が海のすぐそばなので、常々地震が起きたらすぐに津波を意識します。地震よりも津波の方が怖いですからね。
―津波は以前にも経験されたことはあるんですか?
何回か経験していますよ。去年のチリ地震津波も来ましたし。そのときはくるぶしくらいの高さまで水が来ましたかね。20年前くらいには50センチくらいのものを経験しました。身体に触れたのはこの二回ですね。そのとき津波の厄介さを思い知りました。水がじわっと入ってきたと思ったらすぐにすごいスピードで広がっていくんです。引くときは引くときで強い。引き波もすごいんです。海水をかぶるってことは大変なんですよ。電気系統はだめになるし、すぐに酸化してサビてしまう。灯油のタンクなんかが倒れると、油が水に混じって、それがまた厄介なんですよ。
―今回はどうだったのですか。
今回もまっさきに意識しました。揺れが普段と全然違ったし、長かったしね。今回はとんでもない津波になるだろうなと思いました。これほどひどいとは思いませんでしたけど。一生懸命シャッターを閉めて、逃げましたね。逃げることしか考えられなかったです。そのときは一旦酒蔵よりも高いところに避難しました。直接津波は見ていなくて、家が流れていくのを見て「なんじゃこりゃー」と思いましたよ。自分より高い目線のところに船が流れていたりして。小一時間くらいで暗くなってしまって、その晩は車の中で待機しました。

―酒蔵には戻られたんですか?
津波が落ち着いてからです。もろみもタンクも倒れておらず、酒も無事だったことは確認できたんです。それは安心しましたよね。でも、別の不安はありました。
―別の不安?
こんなに酒が残っているけどどうするんだっていう、そういう不安です。震災前の、お客さんの8割は地元の人たちなんです。地元の酒屋さん、スーパー、ホテル・旅館、飲食店など。商売相手が致命的なダメージを受けたわけですから・・・でもそれもだいぶ経ってからですね。地震当日は逃げることとか、安全を守るとか、そんなことしか考えられませんでしたからね。
―従業員のみなさんは無事だったんですか?
15人くらいいたんですが、津波からは守れました。翌朝一回は家に帰しましたが、そのあと顔を出せるようになった人の力を借りながら、最初の一週間は自分たちの食べ物を心配しながら片付けをしていました。その次のステップで、雇用の問題とか、会社がどうなっていくのかとか、考え始めましたね。
―いまは酒づくりを再開されていますが、転機はあったんですか?
はい。発電機を借りることができたんです。3月20日のことでした。それを使えば、酒がしぼれるということが分かったんです。そこからはがらっと変わりました。それまではやれることしかできなかったけれど、しぼった瞬間から、僕の意識の中では「やらなければいけないこと」ということに変わったんです。使命感というんですかね、そういう気持ちが生まれたんです。
―使命感?
地元の人たちが大変ななか協力してくれるんですよ。発電機って簡単じゃないんですよ。1~2トンもある発電機を持って来ないとならないし、運ぶ手段が必要だし、持って来たら配線をする必要がありますよね。発電をし続けるためには燃料が必要だし。こういうのが3拍子、4拍子揃わないと電気は通らない。もしかしたらその発電機があったら誰かが寒さを防げるかもしれない、燃料があればいなくなった人の捜索に回せるかもしれない、買い出しに使えるかもしれない。こんなことやっていいのか、という葛藤がありました。でも、地元の人たちは「なんとか残った生産設備なんだから、がんばれ」と言ってくれたんです。そこから使命感が生まれたというか、「やらなきゃ」と思えるようになったんです。自分の心配がふっとんじゃうくらいの、皆の助けがあったんです。そこからは坂を転げ落ちる勢い、というか、廃業するという考えはなくなりました。

―そこからお仕事を再開されたんですね。
22日に酒がしぼれたときから、アポなし取材というんですかね。新聞社やテレビがどんどんくるようになるわけですよ。「されるがまま」というんですかね。取材されても同じことをいつも繰り返すわけなので、疲れて「帰ってくれ」と言ったこともありましたね、「ああ、なんとか酒がしぼれた!」、このあとなんとかしなきゃな、というときにバンバン来るんです。なんで来るんだって聞くと「こんなに被災地の中で元気のいい場所見たことない」って言うんですよ。そりゃあ発電機は使うし、水もじゃんじゃん流すし、人はいっぱいいるしね。生中継も2本くらいやりましたね。何の番組に出たのかは分かりませんし、どのように映っていたのかも分かりませんけどね。電気がなくてテレビが映らないですから。
―反響はあったのですか?
テレビに出たことで、注文が止まらない、という想定外のことが起きたんです。テレビを見た人たちがメールをくれたり、手紙をくれたりしました。携帯に電話もかかってくるようになりました。
―多くの人に知ってもらえる機会にはなったのですね。
うち、津波で倉庫をなくしたんですよ。そこには酒を詰めるための瓶とか、箱とか、出荷のための段ボールとかが入っていたんですね。酒をしぼったはいいけど、どうしようというときに、ある瓶屋さんから3000本の酒瓶を融通していただいたんですよ。また別の瓶屋さんが自社トラックで運んで来てくださったたこともありましたね。瓶詰めはできても、倉庫にストックしておくことはできないので、ちょこちょこ出荷をして、最終的に本格的に出荷が始まったのは4月に入ってからでした。そういうのをまたマスコミが追っかけるわけです。
―そうするとまたすごい反響があるんですね。
でもこっちは「ウハウハ」というのとは全く違うんですよ。次元が違う。きれいごとに聞こえますけど、使命感みたいなのができてから、走りだしたら止まらなくなってしまって、とにかく酒を出し続けなければ申し訳ない、という気持ちになっていました。4月の下旬にもなるともっと冷静になってきて、地元の水産物が本当にない、ということが分かってきたんですよ。名産は水産物なのに、水産加工する工場などが壊れてしまったんです。よく「被災地のものを買って応援」という話があるけれども、気仙沼に関してはその水産物がない。だからこそ、我々がやらなければ、という使命感がありました。
―売り上げは伸びたんでしょうか?
どん!と増えましたね。でも利益は伸びていないです。入ってくるお金は増えましたけど、その分使うんです。人を雇うこととか、あとは備品をなるべく地元から買うとか。前倒して酒をつくるための設備に投資するとか。お金を地域としても回していくことを考えましたね。このままだと縮まっていくだけでしょう。
たとえば震災前の売り上げが100だとすると、復興支援とかで一時的に上がっているのかもしれないけれど、元々はお客さんの8割は地元ですよ。どん底まで落ちることもあり得るんです。そうならないようにやっていかなければならない。一方では地元の復興もやらないといけないし、もう一方では震災後にうちの酒を新しいものとして受け取った人々に対しても今後につなげていかなければならないんです。それが「いつ終わるだろう」ということも、危機感として持っています。逆にいえば、「いつ終わるかも分からないから、今をきっちりやろう」とも思います。止まったら終わりです。やれない、と言ったらそれで終わりなんです。
―震災を機に生まれた「使命感」で、ここまでずっとやって来られたんですね。
震災前は、よく考えてみればどうでもいいこともやっていたのかもしれないけれど、今は、やること全部に意味があるように思えて来たんです。変わらざるを得ない、ということだったんでしょうね。

聞き手:中村健太(みちのく仕事編集長)
■男山本店公式ホームページ(商品の購入が可能です)