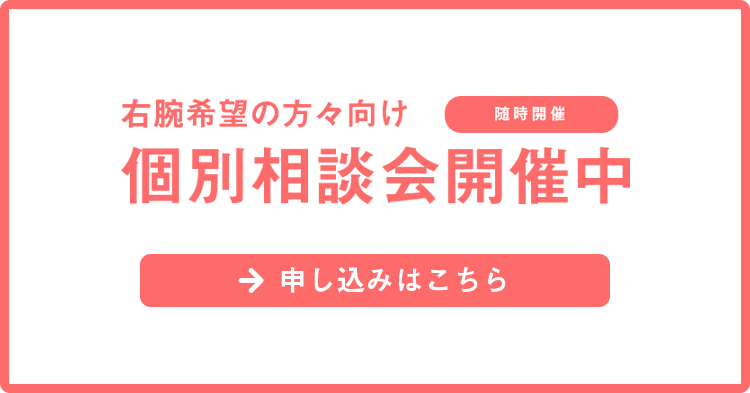私にとっての右腕体験
「忘れないこと」「伝え続けること」に誠実に向き合う
一般社団法人東北復興プロジェクト(宮城県名取市、宮城県多賀城市) 右腕:菊島朋子さん
宮城県名取市の約1,200坪の土地に新設された、農と食の大切さを学び、五感で体験し、味わうことができる「ROKU FARM ATALATA」。こちらのオープン準備から約一年間に渡り、右腕として関わってこられた菊島朋子さんにお話しを伺いました。

― こちらではどのような仕事をされていますか?
広報を担当しています。広報と言っても、お店のメニューなども含めた紙媒体の制作や、ホームページなどを使った情報発信、視察やツアーで団体のお客様がいらした時に施設を案内したり、仕事の幅は広いですね。
― こちらはどういった施設なのでしょうか?
昨年の九月にオープンした施設で、宮城県と山形県出身の経営者六名が共同で経営しています。私のリーダーである島田社長が被災されて避難所で過ごした際、自分は支援される側ではなく支援する側に回らなければと奮起し、食のコンサルティング会社をやっていた関係もあって周囲を巻き込みながら炊き出しの活動を始めました。その時に農業のことや東北の未来について語り合い、意気投合したのがこの六名のメンバーです。アタラタには三軒の飲食店が入っていて、契約農家さんや漁港の方たちと提携しながら旬の野菜や卵、お魚を使った料理を提供している他、東北六県のアンテナショップとしても活用していく予定のコミュニティスペースがあります。
― 震災前はどちらでお仕事をされていましたか?
劇団四季で広報部のウェブ担当として、主に取材活動をしていました。
東北に来たのは、被災地への支援活動として「ユタと不思議な仲間たち」というミュージカルを沿岸の体育館で上演して回ったことがきっかけです。定番のオリジナル作品ではあったんですが、東北の農村部を舞台に描いているだけでなく、“生きる”ということに対して震災にとてもリンクしたメッセージが詰まっていたんです。だから上演後の会場はいつも異様な雰囲気に包まれていて、大人も子どもも心の底から涙されていたようでした。
ある公演の後に激しく泣いているお母さんがいて、「感想を聞きたい」と私が声をかけたら怒ったように拒絶されたことがありました。でも一緒にいたお子さんが頬に涙の痕を残しながら「ぼくも主人公みたいに強くなる。お兄ちゃんいなくなっちゃったけど、ぼくもユタみたいになるんだ。」って言ってくれたんです。そして、初めは拒絶していたお母さんも最後には「あなたたちは私たちに、生きろって言うんですね。分かりました。生きていきます。ありがとう。」って、震えながら、でも凄く強い口調で言ってくれました。そのときに、“ああ、この震災の傷は経験してしまったこの方たちにしか分からない。私たちには、とても計り知れるものではないんだな。”と痛感しました。このエピソードは多くのうちのひとつにしか過ぎないですが、沿岸部を回る先々で様々な出会い、目にした光景、聞いた言葉がたくさんありました。
― 発災から間もない頃に得たこの経験が、全ての原点になったわけですね。
そのあと東京に帰ると大きなギャップを感じました。日常が戻り、まるで何も無かったかのように時計の針が動いていた。でも、自分は東北で聞いてしまった言葉もあるし、彼らの言葉を無駄にしたくない、伝え続けることを止めたくないって思いました。もしかしたら私自身、東京で生活して忘れてしまうのが怖かったのかもしれません。
だから仕事を辞めました。東北に戻り、まずはボランティアから始めようと思い、公演でも訪れた南三陸町に行きました。慣れていないことをやっても逆に迷惑だと思ったので、自分のスキルを発揮できる活動がいいかなと考え、広報を必要としていたところに決めました。二ヶ月ほど活動して東京に戻り再就職しましたが、心ここに在らずの状態。やっぱり私はここじゃないなって思ったんです。だからもうボランティアとしてではなく、きちんと仕事をしようって思い、東北で広報の仕事はないかしらと探していたら右腕の募集を見つけました。
― 色々探していくなかでこちらを選んだのでしょうか?
当時は震災関連の広報の求人が無くて、唯一見つかったのがここでした。要項を見て、記事を書いてくれる方、今の私たちの活動を広く伝えてくれる方を募集って書いてあって、あぁ、もうやりたいって。
― 確かに広報って後回しになる部分ですよね。地元の人たちは、何よりもまず目の前の物事を動かしていかなければならないから。
そうですね。復興に対しては最優先じゃないですよね。

― 前職で培った広報のスキルを生かせるかもしれないと思って応募して、でも実際に働いてみてどうですか?
複雑です。制作物に関する仕事がどうしても多くて。作るのはもともと好きだし、それに「伝える」というプロセスのひとつではあるから、ずれてはいないのかもしれないけど。
でも、私のほんとにやりたいことって、頑張っている東北の人たちを取材して、伝えていくこと。この場所で考えると、例えば東北の野菜農家さんや漁港の方々だと思います。それをアタラタの飲食店で食材として使うのか、ショップの商品としてPRするのか分からないけれど、その人たちがつくったすごく愛おしいものを全国の人たちに知ってもらいたい。
もう“震災”って言っても、聞き飽きている人も多いと思います。だから違うアプローチの仕方で、例えばこんなに東北って美味しいものがあるとか、そこから興味を持ってもらって、実際に来てもらって、食べたり買ったりしてもらう、ということの一端を担えれば。今すぐには難しいけど、近い将来できたら良いですね。
― 日々の業務がありますからね。日常をつくっていくための。
目の前にある仕事が優先されてしまうので。でも本来自分がやりたい仕事が出来ていないのは自分の力不足ですね。
― こちらで働きはじめてどのくらい経ちましたか?
もうすぐ一年になります。今月末で右腕として働くのは終了ですね。
― 今後は?
経営者のみなさんと話しているのは、まず私がここに来た目的を果たしたいということ。それが半年後なのか、一年かかるのか分からないですけども、ズルズルしないで、でもきちんとやり遂げたいと思っています。
― 東北で頑張っている人たちの姿を伝える、というのを形にするまではこちらに残るということですね。
はい、そうです。
― こちらに来て、自分にとって一番の気づきって何でしたか?
昔から受け継がれてきた食文化であったり、地域ごとに育まれてきた郷土芸能であったり、自然の営みの中での知識や知恵が、ここには宝の山のようにあったのかっていうことに気づかされました。あとは東北って古き良き文化がまだ残っているから、日本にとっての“ふるさと”みたいだなって。
― 懐かしいかんじがする、ということですよね。
自然と一緒に生きていて、みんな自然を知っている。津波が来たときも、沖に逃げろって言うらしいですね。それで助かった人もいるって聞いて、ほんと自然の中での生き方を知っているなって思いました。

― 右腕として働くってどうでしたか?これまでの東北との関わり方から変えてみて。
正直、意気込んで来た自分がいました。劇団四季で七年間働いて自信もついてきた頃だったから、もう自分で何でもできるって思っていました。だから、そのスキルを生かした仕事がようやくできる、東北の人たちのために。ほんとに良かったって思って来ました。でも実際ここに来たら振り出しに戻って、ゼロからのスタートで精神的に辛い思いもしました。
― 早い段階で自分はゼロだって気づけましたか?
すぐ気づきました。でも、気づいてからイチにするまでが長かったです。必要とされていたのは自分じゃなかったかもって思ったこともありました。帰るべきかもしれないと思ったことも実はあったし。でも本心は帰るなんてことできない、帰りたくない、というジレンマ。でも、目の前のことをこなしていくうちに、自分のやるべきことが分かってきたのかもしれません。
― 「右腕」ってどんなものだと思いますか?
文字通りにいってしまうと、現場を担うというか、リーダーの発するものに応えるというか。影武者なのか、或いは二人三脚で行く相手なのかなと思うんですけど。
―難しいポジションですよね。では、自分なりにどういう存在でありたいと思っていますか?
難しいですね。“叶えてあげられる人”でありたい。全然できてないからこれは理想ですね。
右腕に応募する人たちって、震災復興で力になりたいって思いを持って来ると思います。でも、私が携わっているのは商業施設。どうしてもビジネスとして成立させることに注力してしまう面があって。そんな時によく「菊島もせっかく来てくれたから、やっぱり震災のことや復興のためになることを、きちんとやっていかないといけないよね。」って言われるんですよ。だから右腕って、東北がんばっていこうよって気持ちを忘れないひとり、みたいなことなのかなって思います。
― みんながふと原点に立ち返るための存在、ということですね。これから右腕として東北に来てみようかと考えている人にアドバイスはありますか?
柔和な心で。壁にぶつかるのは当たり前だと思います。でも信じることですね。リーダーを信じて、地元の人を信じて。誠実な気持ちを忘れなければ、きっとやっていける。誠実にっていうのは、ほんとに忘れないようにしようと思っていて。地元の人たちに対しては絶対に誠実に。あと迷惑はかけちゃいけない、というのが私のルールです。押し付けちゃいけない。郷に従えということかな。あとは、楽しめたら勝ちですよね。
震災から三年以上が経った今も、「忘れないこと」そして「伝え続けること」に対して向き合い続けている菊島さん。短い時間でしたが、東北に対するたくさんの想いを聞かせて頂きありがとうございました。
聞き手・文:中村真菜美(本稿は一般社団法人APバンク様より寄稿頂きました)